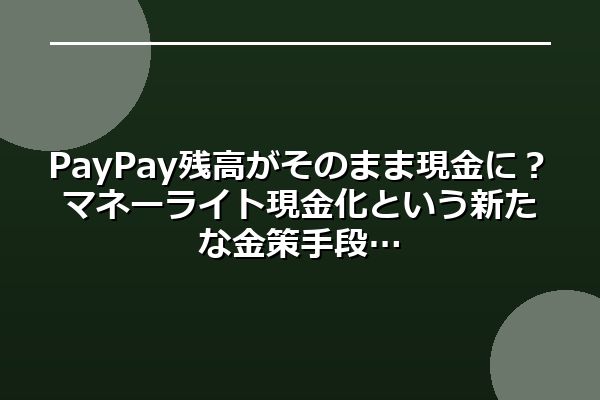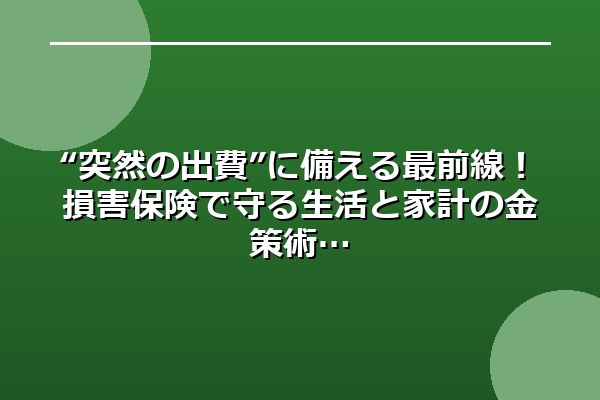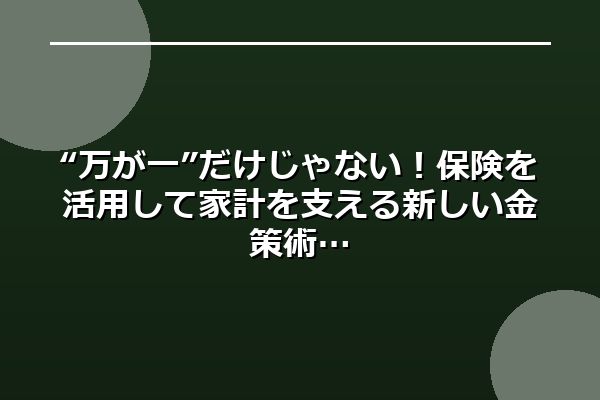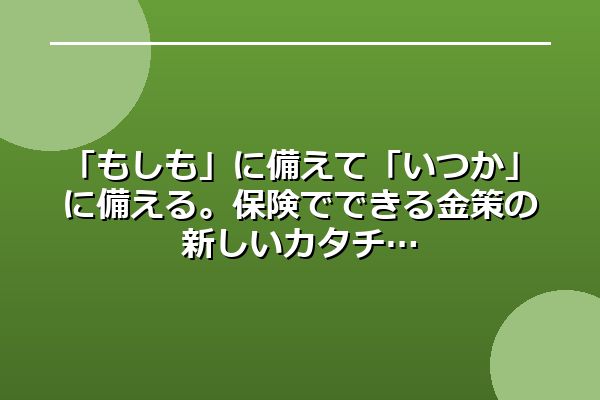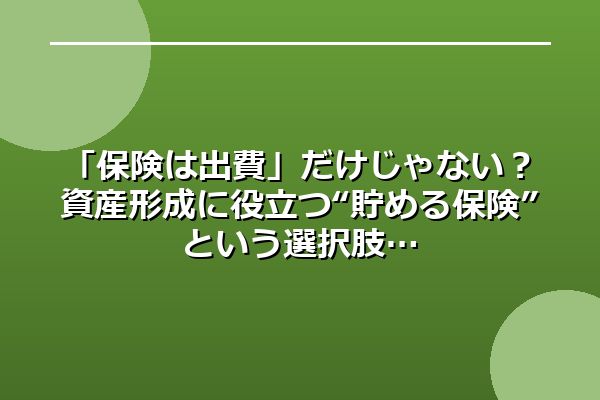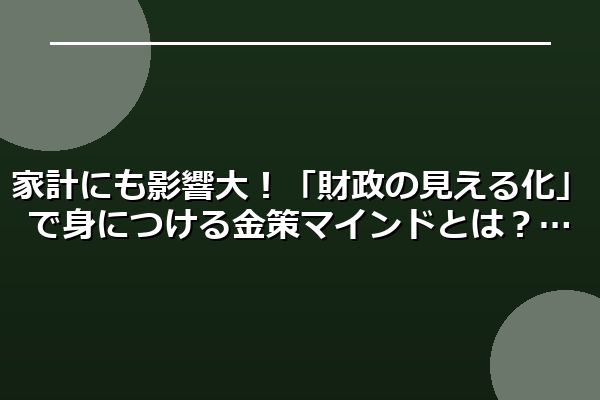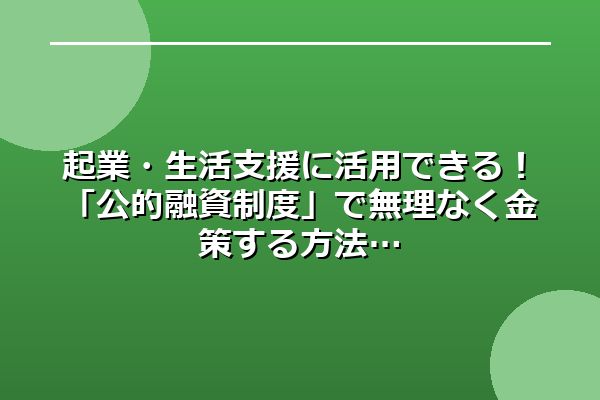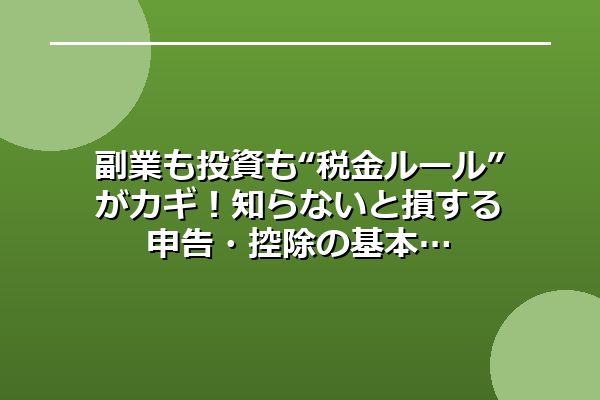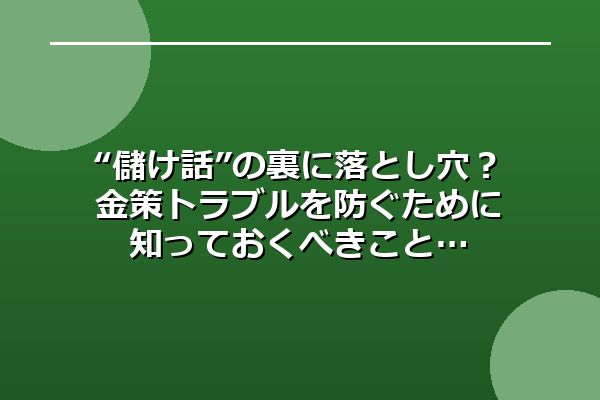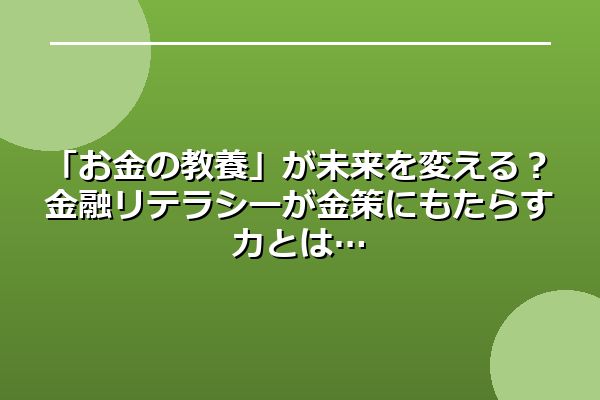キャッシュレス決済が一般化した今、「PayPay残高はあるのに現金が足りない」という状況に陥ったことはありませんか?
そんなときに注目されているのが「PayPayマネーライトの現金化」です。
電子マネーの流動性を高める新たな金策手段として、一部のユーザーに広がりを見せています。
PayPayマネーライトとは?
PayPay残高には「PayPayマネー」と「PayPayマネーライト」の2種類があります。
マネーライトは、キャンペーンやクレジット経由でチャージされたもので、送金や出金には対応していません。
そのため、使い道が限られている分、現金が必要なときには不便に感じることがあります。
なぜ“現金化”が必要とされるのか
マネーライトは主にネット決済や店頭での利用に限定されており、公共料金の支払いやATMでの引き出しには使えません。
こうした制約のなかで、「現金が必要なのに使えない」という矛盾を解消するため、現金化ニーズが生まれています。
現金化の方法と注意点
PayPayマネーライトを現金化する方法として一般的なのが、“買取形式”のサービスの利用です。
ギフト券や商品をPayPayで購入し、それを買取業者に売却するという流れが多く、
業者によってはLINEでのやり取りから即日振込まで対応してくれるところもあります。
おすすめサービスの一例
スムーズな現金化と手数料の明確さで信頼されているのが、
PayPayマネーライト現金化業者です。
PayPay残高を活用したいけれど、現金がすぐに必要な方にとって、便利かつスピーディーな選択肢となるでしょう。
注意点:規約や手数料に要注意
PayPayの利用規約では、マネーライトの不正利用や換金を禁じている可能性もあるため、
業者選びや利用方法は慎重に行う必要があります。
また、換金率や手数料によって実際に受け取れる金額が減るケースもあるため、事前の確認は必須です。
まとめ:PayPay残高を“使えるお金”に変える柔軟な金策
使い道が限られているPayPayマネーライトを、必要に応じて現金として活用できる手段があることは、
金策の幅を広げるうえで非常に有効です。
ただし、規約違反やトラブルを避けるためにも、信頼できる業者の利用と慎重な判断を心がけましょう。